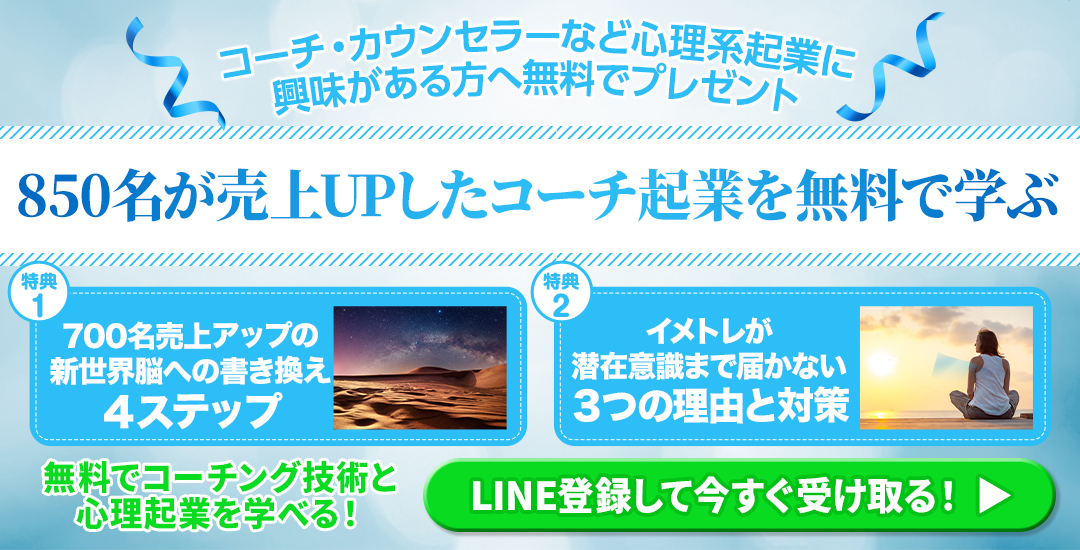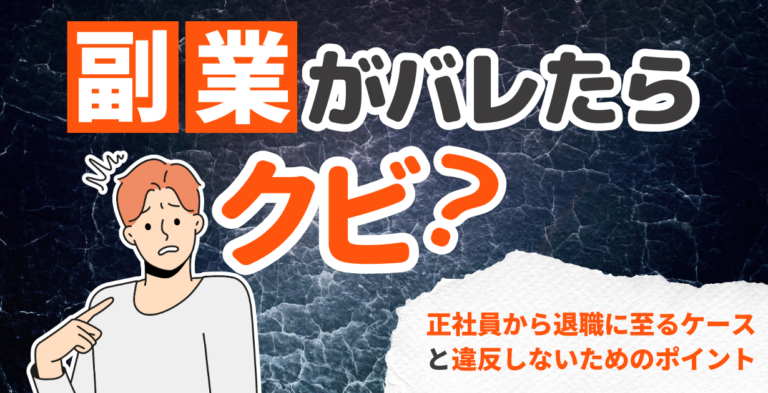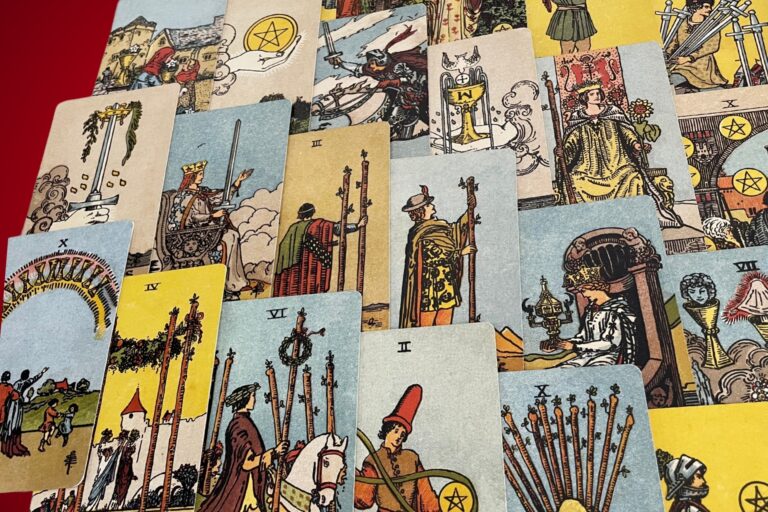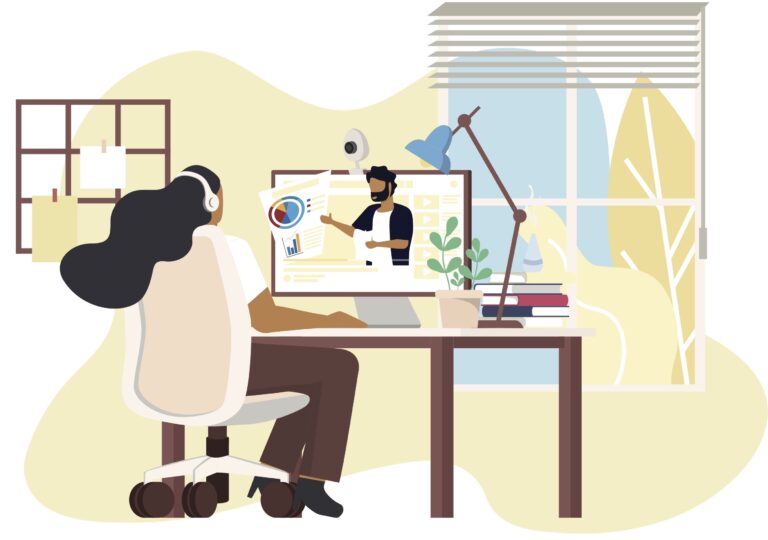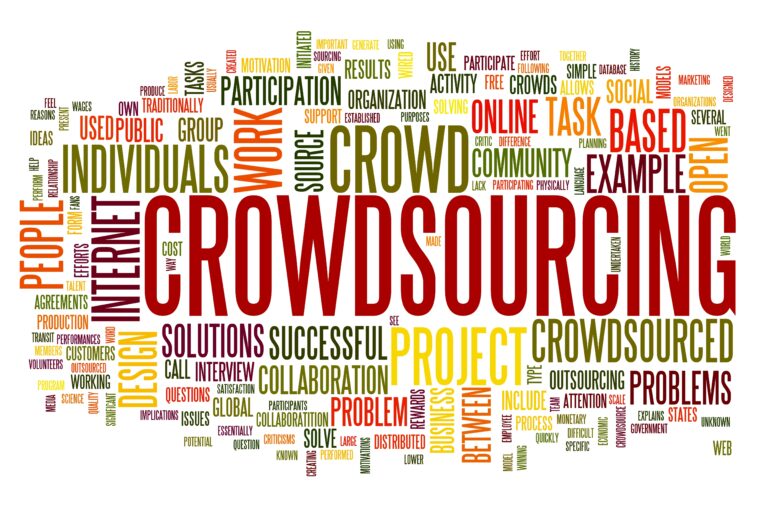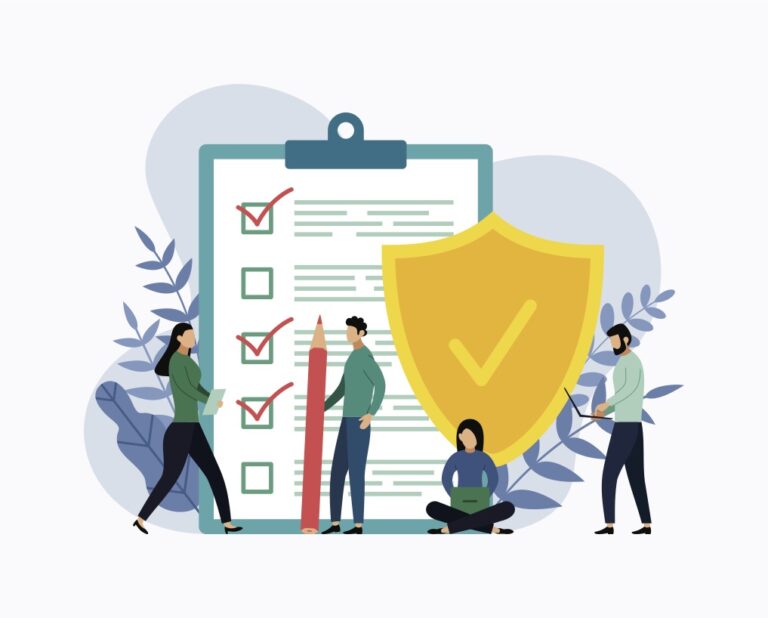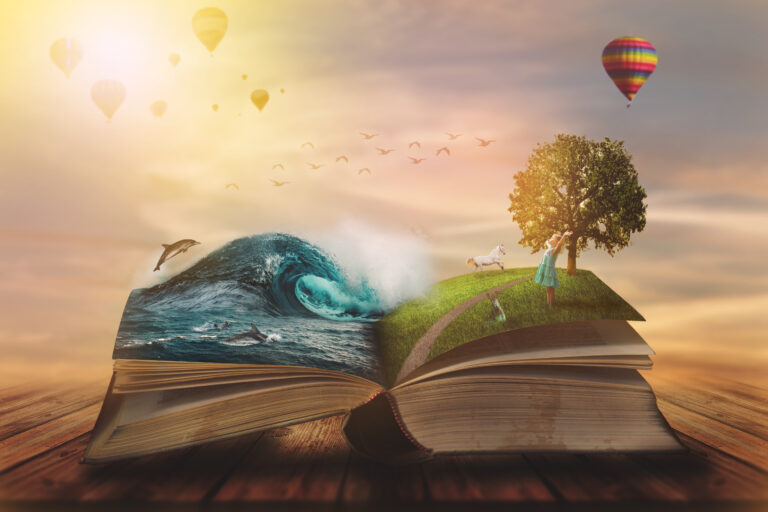副業を検討している方の中には、「副業禁止は法律的な効力があるのか」「副業がバレたときに懲戒処分を受けないのか」と疑問を抱く方がいます。
そこでこの記事では、副業を禁止する法律があるのかについてお伝えするとともに、副業に関する法律改正の歴史や副業をする際の注意点を詳しく解説します。
目次
副業を禁止する法律はある?
まず、副業を禁止する法律があるかについて解説します。
会社員の副業は法律的には禁止されていない
会社員の副業は原則、法律によって禁止されていません。また、労働者が本業以外で収入を得ることについて定めた法律もないため、副業自体が法律違反になることはありません。
しかし、就業規則として副業を禁止している場合があります。もし、就業規則を守らずに副業を行ってしまうと、何らかの処罰やペナルティを受けてしまう可能性があります。
公務員は副業を法律で禁止(制限)されている
公務員における副業は原則日本の法律で制限されています。
「国家公務員法」と「地方公務員法」という法律によって副業は制限されており、営利目的もしくは自ら営利企業を営んではいけないと定義されています。
これらの法律により、公務員の兼業や副業は厳しく制限されているので、公務員の方は基本的に副業を行うことはできません。
関連記事:公務員の副業はどこまでできる?注意点、バレたときの処分も解説
就業規則は法律ではない
よく就業規則と法律を混合して考える方がいますが、全くの別物です。
勤めている会社には就業規則といった会社独自のルールが存在します。このルールは労働者と使用者の間に結ばれる契約であり、労働者は会社が定めたものを守る必要があります。
また、会社によっては就業規則で副業を禁止している場合もあり、違反した場合は懲戒の対象となる旨が記載されていることが多いです。
就業規則に副業を禁止するルールが載っていたのにも関わらず副業をしてしまった場合は、会社が制定したルールに違反することになるので、契約違反となり減給や謹慎などの対象になる可能性があります。
ただし、就業規則で副業禁止と明言されていたとしても、憲法や法律の違反ではないため、法的拘束力は原則ありません。
関連記事:副業とは?兼業や複業との違い、メリットと注意点を紹介
副業や兼業における法律改正の歴史
ここからは、副業や兼業における法律改正の歴史について紹介します。
2018年に「モデル就業規則」が改正されて副業解禁
2017年に「働き方改革実行計画」という副業や兼業の解禁を促す環境整備が行われるようになりました。
その一つが「モデル就業規則」です。モデル就業規則とは、企業が就業規則を作成する際のモデルとなるよう、厚生労働省が作成した見本となる就業規則です。
モデル就業規則から、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という一文が削除されたため、副業が制限されなくなったのです。
しかし、副業を禁止している会社はまだまだあります。すべての会社で副業が解禁されているわけではないので、注意が必要です。
2020年に副業・兼業者への労災保険法が改正
2020年9月には「労働者災害補償保険法」が改正されました。
この法律が改正されたことで、従業員が労働時に怪我や病気が発生した場合に、労災保険として支払われる金額が勤務先一つだけではなく、すべての勤務先の給料をもとに計算されるようになりました。
また、今までの労働災害は各勤務先の労働時間や業務内容をもとに評価していましたが、改正後は一つの勤務先だけでなく、複数の勤務先での実情などを踏まえ、総合的に判断されるようになりました。
それらの総合的な判断と評価によって労働災害か労働災害ではないのかが判断されるようになったのです。
2022年に副業・兼業者への雇用保険法が改正
2022年4月から「雇用保険法」が一部改正され、副業をする方がさらに雇用保険に加入しやすくなりました。この法律改正により、65歳以上の高年齢被保険者を対象に特例が施されます。
従来は、1事業所で週20時間以上働いている従業員を、雇用保険の被保険者として定めていました。
法改正後は、65歳以上ですべての勤務先の労働時間の合計が週20時間以上の従業員が、雇用保険の適用対象として認められるようになりました。
高齢者でも働きやすい環境が構築できており、複数の勤務先がある方の福利厚生の向上につながっています。
ただし、この特例を適応させるには、公共職業安定所で専用の届出を行う必要があります。条件を満たせば勝手に被保険者になるわけではない点に注意しましょう。
副業を認めている企業の例
副業を解禁する企業は年々増えてきています。ここからは、副業に対して先進的な姿勢を見せている企業を紹介します。業界や会社によって副業解禁の方法にも大きな差があるため、ぜひ参考にしてください。
ヤフー株式会社(Zホールディングス株式会社)
IT企業大手で、Yahoo!を運営するZホールディングスは、「他社との雇用契約を結ばない」「本業に支障をきたさない」「激務でない」などの条件を満たす場合に副業を解禁しています。
副業をする場合は、自分で申請を行い受理されることで可能になります。また、ヤフーは無制限リモートワークといった面白い働き方を打ち出しており、飛行機通勤も許可されています。
さらに、2022年の4月からは居住地を自由化しており、国内であればどこでもヤフーで働くことができるようになったのです。
場所を選ばず働くことができるため、他の副業が行いやすい環境が整っている会社といえます。
三菱地所株式会社
就職希望ランキングにおいて毎年トップに君臨している三菱地所は、1カ月に50時間以内という制限を設けて、社員の副業を許可しています。
さらに、副業を解禁するとともに、新事業に関わる人材を副業や兼業限定で募集するなど、外部人材の登用も積極的に行っています。
これまで、副業や兼業などの働き方を導入していない会社でしたが、今では新しい働き方を認め、導入する流れに組み込まれているのです。
社外に重要な仕事を頼ることは、セキュリティ上避けがちですが、三菱地所では人材を広く活用したいという姿勢が見受けられます。
みずほフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループは、2019年から業界先駆けで副業の解禁を行いました。
社外での副業はもちろん、スタートアップを進める社外兼業も解禁しています。2021年時点で、200件を超える副業申請が行われ、一定の成果を上げています。
また、週休3日制や週休4日制の採用なども行っています。働き方を自由にすることで、副業にも重点を置いて取り組むことができるようになっています。
株式会社エイチ・アイ・エス
株式会社エイチ・アイ・エスは、2018年より「楽しい職場づくり」の実現を目指し、新しい働き方制度を導入しています。
制度は4項目あり、「副業の解禁」「時短社員へフレックス制度の導入」「在宅勤務のトライアル開始」「再雇用制度の導入」です。
通訳ガイドに積極的に取り組むことができる環境を整備し、副業などの社外経験を生かしながら、本業につながるスキルアップを目指しています。
また、在宅勤務のトライアルやフレックス制度により、副業に向ける時間も増えてきているといえます。
日産自動車株式会社
日産自動車は、早い段階で副業を認めた企業の一つです。
日産では2009年から副業を一部容認しています。副業を容認した背景には景気悪化と社員の賃金カットなどが原因しています。
本業が休業日であれば、8時間以内での副業が認められているため、幅広い業種に挑戦できます。
企業が副業を解禁するメリット
副業を解禁するにあたって、会社側には以下のようなメリットがあります。
- 社内では手に入らない知識やスキルを習得できる
- 労働者自身の自主性を促せる
- 優秀な人材の獲得、流出を防止しながら競争力を向上させられる
- 社外から新しい知識やスキル、情報や人脈を持ってくることができる
上記のように、従業員のスキルアップが図れるため、副業を行うことは企業側にも大きなメリットがあります。
また、副業を許可することで従業員の満足度も高くなるため、離職率を下げる対策としても有効です。
企業が副業を解禁するデメリット
反対に副業を解禁することで、企業側には以下のようなデメリットがあります。
- 就業時間が長くなることで、労働者の体調管理や健康管理が難しくなる
- 職務専念義務や秘密保持義務、競業避止義務を破られる可能性がある
企業としては、従業員の就業時間や健康管理など、職務専念義務や秘密保持義務を守るような取り組みを実施しなければなりません。
従業員の福利厚生に関するコストが上がる可能性があるため、企業にとってはデメリットといえるでしょう。
副業をしたことで懲戒になる場合
ここからは副業をしたことで、懲戒になるケースについて解説します。
会社の副業禁止・制限に違反した場合
会社側が就業規則で副業を禁止していたり制限していたりしたとしても、副業を行ってすぐに解雇されるということはほぼありません。
副業を行うことを規制する法律はないため、重大な契約違反として扱われる可能性は低いです。
また、過去に裁判所の判例で、「職場秩序に影響せず」「労務提供に支障を生ぜしめない程度であれば」懲戒処分にはならないと判決が出ています。
このため、会社側が解雇などの大きなペナルティを課される場合は、不当だと訴訟し取り消しできる可能性があります。
労務提供上の問題がある場合
副業をしていたとしても、解雇などの懲戒を受ける可能性は低いと紹介しましたが、副業が原因で本業の労務提供に影響がある場合は例外です。
労務提供に影響があるケースとは、例えば「本業の勤務中に副業を行った」場合や、「副業を行いすぎて体調や健康を崩してしまった」場合があげられます。
これらのケースの場合、従業員の副業が理由で本業に悪影響が出ているため、過去の判決でも懲戒は正当であると判決が出ています。
競業をして本業の利益を害する場合
競業している他社で副業をした場合も、懲戒を受ける可能性があります。
競業している他社とは、本業と同じ分野で競合にあたる会社を指します。例えば、銀行に勤めている場合は、金融系の会社が該当します。
これらの競業をしている他社でサービスや商品を提供した場合、本業での業務に影響を与える可能性があるため、懲戒される可能性があります。
また、競合他社の場合本業の業務上で知り得た情報を、副業を行う競合他社に情報を渡してしまう場合も懲戒の対象になります。
本業の機密情報を漏洩した場合
本業で手に入れたデータや情報を副業で活用するといったことは、基本的に懲戒の対象になります。
このような行為は本業の企業に対して損害を与えることにもなるため、懲戒処分の対象になるかもしれません。
また、本業の企業側が訴えた場合、不正競争防止法違反などの罪に問われる可能性もあります。罪の重さは実際に企業に与えた損害によって異なりますが、民事、刑事両方の罪に問われる可能性があります。
企業の名誉や社会的信用を損なう副業をした場合
副業を通じて、企業の名誉や社会的な信頼を落とす行為をしていた場合も、懲戒処分の対象となるかもしれません。
例として、反社会的勢力と関わる副業を行うなど、本業の企業の名誉や信用を著しく低下させるものは、懲戒の対象になる可能性があります。
また、会社によって信用を得ているポイントが異なるため、本業の会社の不利益にならないかどうかを事前に確認しておきましょう。
副業・兼業をする際の注意点
副業や兼業をはじめるときは、本業の会社とトラブルにならないようにすることが大切です。ここでは、副業や兼業をはじめる際に注意すべき点について解説します。
労働契約や就業規則を確認しておく
副業をはじめるときは、労働契約や就業規則を必ず事前に確認しておきましょう。
労働契約には副業が許可されているのかについて記載されており、就業規則には副業を行うときの手続きが載っています。
労働契約や就業規則などをよく確認のうえ、副業が許可されているのか、もしくは副業が許可されている場合は、どのような条件のもと副業を行うことができるのかについて確認しておきましょう。
労働時間を管理して働きすぎないように注意する
副業をはじめるときには、本業と副業の両方の労働時間を管理して働きすぎないように注意しましょう。副業に時間を費やしすぎて、本業に集中できない場合は、会社側から副業を禁止される可能性もあります。
また、本業への影響が大きい場合、懲戒の対象になってしまう可能性もあります。副業をすることによって収入が増えるなどのメリットがある分、本業が手につかなくなってしまうといったデメリットもあります。
このような状態を避けるため、働く時間を明確にして、本業の時間は本業を行う、副業の時間は副業を行うなど、メリハリをつけたスケジュールを立てていく必要があります。
本業の時間に副業をするのは多くの会社の就業規則の違反にあたる可能性がありますので、本業中に副業を行うのは絶対にやめておきましょう。
本業への義務違反にならないようにする
副業を行うにあたり、本業の職務専念義務や秘密保持義務、競業避止義務などに反することがないように注意する必要があります。
本業の業務に悪影響を与えるような副業を行うと、副業を許可している会社であったとしても、懲戒の対象となる可能性があるのです。
具体的には、本業と同じ分野の副業を行ったり、本業の情報を副業先で伝えたりすると、義務違反として処罰されるかもしれません。
副業を行うときには、事前に副業の内容や会社の情報を確認して、義務違反にならないか確認しておきましょう。
必要に応じて確定申告を行う
副業での収入が20万円を超えると確定申告が必須になります。源泉徴収で税金を納めている方でも、自分で税務署へ確定申告を行い、直接納税する必要があるため注意してください。
また、副業の種類によっては給与所得以外の所得に分類されるケースがあるため、副業の内容と所得の関係性の確認が大切です。
さらに、控除や扶養についての勉強をしないと、節税面で損をする可能性もあるため、確定申告前にしっかりと学習しておきましょう。
関連記事:副業すると税金はどうなる?20万円ルールの注意点も解説
副業についての最新の法律を確認しよう
前述のとおり、副業を解禁している企業は多く、今後も増えてくる可能性が高いです。
また、副業は法律上、直接制限するものはないため、業務違反とならないよう気を付けながら副業を選ぶことで、トラブルを避けられるでしょう。
なお、昨今は社会的に副業を解禁する流れがあるため、今後副業がしやすくなる法律に改正される可能性もあります。